1974年生。立教大学大学院文学研究科博士課程後期課程修了、博士(文学)。現在、神奈川大学国際日本学部教授。日本近現代文学・演劇・美術。著書に、『昭和一〇年代の文学場を考える 新人・太宰治・戦争文学』(立教大学出版会、2015)、『文学と戦争 言説分析から考える昭和一〇年代の文学場』(ひつじ書房、2021)、『戦時下の〈文化〉を考える──昭和一〇年代〈文化〉の言説分析』(思文閣出版、2023)ほか。論文に、「萱野二十一「道成寺」同時代受容分析」(『国語国文』2024. 9)、「見えにくい世界/新しい景色──宮永愛子のオペレーション」(『人文研究』2024. 9)ほか。
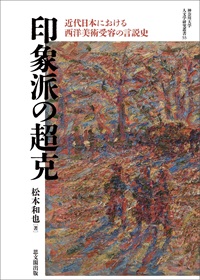
インショウハノチョウコク
印象派の超克
近代日本における西洋美術受容の言説史
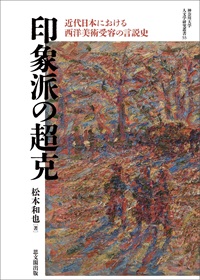
-
体裁A5判・336頁
-
刊行年月2025年10月
-
ISBN978-4-7842-2115-8
著者・編者略歴
内容
モネやルノワールなど、日本人がこよなく愛する印象派は、どのようにして日本の美術界に受け容れられてきたのか?
明治後期に流れこんだ印象派は、日本の洋画界に新たな波をもたらした。なかでも「日本のモネ」と称された洋画家・山脇信徳は、その絵画表現によって注目を集め、印象派の是非をめぐる論争の渦中に立った。第三回文展で褒賞となった《停車場の朝》や、その数年後に描かれた《夕日》などの山脇作品は、画壇・文壇を横断した二度の大論争を巻き起こす。それは、印象派以降の西洋美術が日本に受容される際に生じる反発や葛藤の、いわば象徴的事例であった。
本書では、山脇信徳とその絵画表現を結節点として、齋藤輿里、高村光太郎、岸田劉生、そして白樺派など、時代のキーパーソンの言論を丹念に読み解きながら、西洋美術の新潮流が日本にもたらした文化的衝突、そしてそれがしだいに「日本化」され超克されていくさまを明らかにしていく。
★★★編集からのひとこと★★★
今でこそ多くの日本人に愛される印象派。その独特の重ね塗りは「筆触分割」という技法によるものらしいのですが、それが「醜い」とさえ評されていた時代がありました。何が美しく、何が美しくないのか。あるいは何が芸術とそれ以外とを隔て得るのか。それは現代のアートシーンにも通底する問いであり、その意味で時代は絶えず繰り返されているのかもしれません。
本書では、明治晩年の日本で、絵画の新技法が反発を招きながらも、次第に受け入れられていった過程を跡付けていきます。その議論を通して、時代を越えて鑑賞者・批評者に突き付けられる問いにも迫る1冊です。
目次
はじめに 日本の印象派
Ⅰ
第一章 山脇信徳へのアプローチ――洋画史・〝日本のモネ〟・言説史
第二章 西洋美術の新傾向をめぐる言説史――印象派、ポスト印象派を中心に
第三章 帰朝する新進洋画家――パイオニアとしての有島生馬・齋藤與里・高村光太郎
Ⅱ
第四章 「生の芸術」論争・再考――「DAS LEBEN」/「地方色」からみた山脇信徳《停車場の朝》
第五章 山脇信徳作品展覧会をめぐる「絵画の約束」論争・再考――「自己」か「公衆」か
第六章 山脇信徳「断片」の歴史的意義──フォーヴィスム/エキスプレッショニズムへ
Ⅲ
第七章 「自然」と「生活」をめぐる岸田劉生の芸術論――白樺派言説を補助線として
第八章 ヒュウザン会(フュウザン会)展覧会の同時代評価──印象派以降の展開
第九章 「心的印象」を象徴的に描くこと──萬鐵五郎の「新しい原始時代」
結論 印象派の超克
初出一覧
あとがき
紹介媒体
-
『美術の窓』第507号
2025年12月
新刊案内






