アート・コレクター、横浜美術大学教授、森美術館理事。1963年東京都出身。東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻後期博士課程修了。博士(学術)。
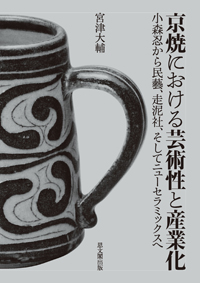
キョウヤキニオケルゲイジュツセイトサンギョウカ
京焼における芸術性と産業化
小森忍から民藝、走泥社、そしてニューセラミックスへ
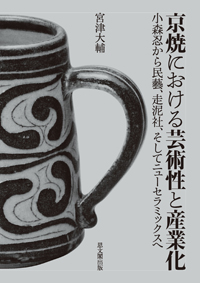
-
体裁A5判・324頁
-
刊行年月2025年10月
-
ISBN978-4-7842-2101-1
著者・編者略歴
内容
近代京焼には、古都としての歴史性を背景に、登り窯を中心とした制/製作者による緊密なコミュニティーや、数理的思考の涵養と技術・情報のハブとして機能した京都市立陶磁器試験場の存在など、独自の進化・発展因子が形成された。このような環境のなかで、小森忍をはじめ、民藝運動や走泥社、さらにはニューセラミックスなど、多様な潮流が生まれ、育まれた。
本書では、これらの潮流を横断的に捉えることで、従来の工芸史の枠組みを超えた、オルタナティブな陶芸・窯業史の提示を試みる。近年活発化する「工芸」「デザイン」「アート」領域の再定義を背景に、京焼における芸術性(陶芸)と産業化(窯業)の拮抗・併存がもたらす製陶の新規性と発展を、複眼的に考察する。
目次
序
はじめに
(1) 本書における「京焼」の定義
(2) 「工芸」と「純粋芸術」の関係性
(3) 小森忍の再評価
京焼・革新の歴史が育む伝統
(1) 京焼の起源から江戸時代初期まで
(2) 京焼の隆盛:江戸時代中期から後期にかけて
(3) 京焼の近代化:幕末期から明治時代にかけて
第1部 小森忍の陶芸と窯業(1)
第1章:京都市立陶磁器試験場時代―数理的思考の濫觴
1 京都市立陶磁器試験場の設立背景とその歴史
2 師・藤江永孝譲りのドイツ流燃料と焼成論の実践
第2章:満鉄中央試験所時代―中国倣古陶磁器技法の再現と産業化
1 満鉄中央試験所での業務
2 満鉄マンの自由闊達な気質
第3章:満洲・匋雅堂時代―茶道具から鑑賞陶器、建築内装材へ
1 満鉄からの独立と匋雅堂設立
2 匋雅会の特徴
3 匋雅堂による建築内装材
4 同時代の朝鮮における高麗青磁再現品
5 離満と満洲時代の総括
第2部 小森忍の陶芸と窯業(2)
第1章:瀬戸時代(1)―山茶窯による建築内装
1 山茶窯の開窯
2 陶製タイル制作への飽くなき挑戦
3 名古屋城意匠を取り入れた庁舎と、地場産業の陶製建材
4 銀座カフェー文化から、ビヤホールライオン銀座七丁目店の陶製内装へ
第2章:瀬戸時代(2)―山茶窯、名古屋製陶における洋食器の東洋化
1 山茶窯における西洋食器の東洋化
2 名古屋製陶鳴海工場での洋食器大量生産
3 瀬戸時代:山茶窯、名古屋製陶における仕事の総括
4 戦中・終戦後期―佐那具陶磁器研究所から北海道へ
第3章:総括・小森忍の仕事―芸術性と産業化の拮抗・併存
第3部 継承される京焼の革新性
第1章:戦時下における京焼の技術進化
1 京焼における理化学陶磁器の黎明とその背景
2 戦時下における京焼の技術進化
第2章:京焼における芸術潮流
1 「民藝」の誕生と発展
2 民藝理論が内包するオリエンタル・オリエンタリズム
3 陶芸をデザインへと架橋する富本憲吉の作陶思想
4 走泥社によるオブジェ焼き
第4部 窯業からニューセラミックスへ―京焼が生む最先端技術
第1章:京焼におけるニューセラミックスの黎明―村田製作所
第2章:京焼におけるニューセラミックスの発展―京セラ
結―京焼にみる芸術性と産業化の拮抗・併存
京焼における革新性創出の要因
総括:芸術と産業の併存が生む、工芸と純粋芸術間の相互架橋
(1) 京都市立陶磁器試験場で養われた数理的思考
(2) 満洲時代:満鉄中央試験所、匋雅堂における中国倣古陶磁器の研究・制作実践
(3) 「鑑賞陶器/陶磁器」分野の登場による、美術品市場の変化
(4) 人々の思考、身体的関与による空間形成が生む、建築内装タイルと現代アートの相似形
(5) 洋食器の東洋化と大量生産化による、デザイン領域への架橋
おわりに
あとがき
注釈
参考文献
索引
紹介媒体
-
『月刊美術』第51巻第12号
2025年12月
新刊案内






